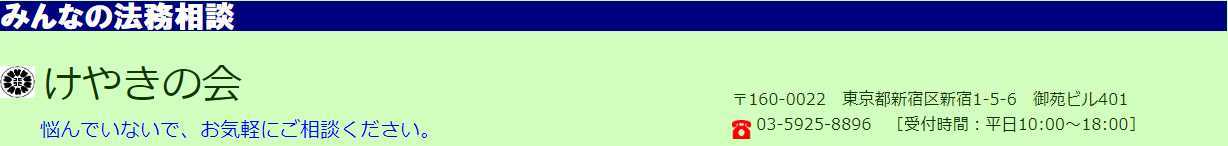契約書
はじめに
現代社会はビジネス社会と言っても過言ではありません。そしてそのビジネスは、会社同士や会社と個人の契約の積み重ねで成り立っています。
契約書を作っておかなかったために、契約について争いになったり、インターネットでダウンロードした契約書を使ってトラブルになったという相談は絶えません。
そのようなトラブルのうち、8割方は事前に契約書をきちんと作成しておけば避けられたようなものばかりです。
少しの手間を惜しんだばかりに、トラブル処理のために、契約書作成にかかる数十倍もの時間・費用を費やさなければならなくなることも珍しくありません。
そういう観点からも、法的に正確である契約書の重要性は明白です。
さらに、ビジネスの世界において、契約書は法的リスクを回避するという側面のほかに、取引の受注率を上げたり、業務を効率化したりという側面ももっています。
ここではその契約書の基本をなるべくわかりやすく説明していきたいと思っています。
↑トップへ戻る
1.契約とはなにか?
契約は、一方の当事者からの申込と、他方の当事者の承諾という意思表示によって成立します。そしてそのビジネスは、会社同士や会社と個人の契約の積み重ねで成り立っています。
例えばコンビニエンスストアでおにぎりを買物する場合、レジにおにぎりを持って行くことが申込に該当し、コンビニエンスストアの店員が、レジで会計を行うことが承諾に該当します。
簡単に説明すると、買いたいと思う意思表示と売りたいという意思表示が、お互いに合致して成立することです。
こうした日常の買い物一つとってみても立派な契約です。
つまり、日本では、当事者の合意さえあれば、契約は基本的に口約束だけで成立します。
そしてその契約内容は原則として自由に決められ、法律よりも当事者同士で決められたことが優先されます。
そして、その契約には4つの契約自由の原則があります。
| ①締結自由の原則 | 契約自体を締結するか、しないかを自由に決定できる。 |
| ②相手方自由の原則 | 契約を結ぶ相手方を自由に決定できる。 |
| ③内容自由の原則 | 契約の内容を自由に決定できる。 |
| ④方法自由の原則 | 口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる。 |
もっともこの4つの原則には、各法律の制限によるいくつかの下記の例外があります。
事業者への規制と消費者への保護のための例外
①締結自由の原則 契約の締結を自由に決定できない
具体例 ⇒ 医師は、正当な事由がなければ、診察治療を拒否できない (医師法)
②相手方自由の原則 契約の相手方を自由に決定できない
具体例 ⇒ 労働者を雇用する場合、使用者は、その労働者が労働組合に加入しようとしていることを理由として、その労働者との労働契約の締結を拒否できない(労働組合法)
③内容自由の原則 契約の内容を自由に決定できない
具体例 ⇒ 事業者と消費者との契約の場合、消費者にとって一方的に不利な契約内容は無効となる(消費者契約法)
④方法自由の原則 必ず契約書を使用しなければならない
具体例 ⇒ 建設工事の場合、建設業者と施主との間の建設工事請負契約は、必ず書面で行わなければならない(建設業法)
↑トップへ戻る
2.円滑なビジネスのために
さてビジネス上の契約は、口約束で契約を結んでしまうと、リスクや経済的利損益が大きいため、仮にトラブルが起きた場合、裁判では、契約の成立や契約の存在が客観的に立証されなければ、成立していない、存在していないと判断されてしまう可能性があります。そこで、裁判で契約の存在が否定されるという事態を避けるために、証拠としての契約書が重要になります。
一般的なビジネス上の企業間の契約は、リスクや経済的利益が大きければ大きいほど、口頭ではなく、契約書によって結ばれます。
口頭による契約
メリット ⇒書類を準備することなく、手続きが簡単。
デメリット⇒契約内容を確認出来ないので、トラブル発生時の対応ができない。
裁判になった場合、他の証拠がなかったり、証人がいなかったりすると、契約の内容や契約の存在そのものを立証できない。
契約書による契約
メリット ⇒契約内容を確認できるので、トラブル発生時の対応ができる。
裁判になった場合、最も証拠能力が高い文書として提出できる。
企業の場合、担当者が変わっても契約内容を確認することができる。
デメリット⇒書類を準備しなければならず、またサインや押印が必要なため、手続きが煩雑である。
企業間で契約書を使用する理由
①多額の金額のやりとりの証拠を残す(不動産売買契約など)
②複雑な権利関係を確認できるようにする(ライセンス契約、フランチャイズ契約など)
③業務の内容を確認する(業務委託契約、コンサルティング契約など)
④法律が未整備の契約を補完する(リース契約など)
ところで、契約には契約当事者の権利・義務が規定されます。つまりそれはビジネス上で言うと提供するサービス・対価のことです。
例えば会社どうしの製品売買の取引契約の場合、受発注、納入、検査、請求、支払いなど、取引先とのあらゆる手続きが、契約書によって規定されます。つまり契約書によって、契約当事者間でとり行われるサービスとその業務プロセスが明確になるということです。
| 売り手側 | 買い手側 | |
| 権利 | 代金の支払いの請求 | 商品引き渡しの請求 指定場所での受領 品質保証の要求 アフターサービス |
| 義務 | 商品の引き渡し 納期の遵守 売り手指定場所への納品 品質保証 アフターサービス |
料金の支払い 商品の検査 |
そして、そのような手続きが明確に記された契約書は事務処理のマニュアルになるということです。
優れた契約書は事務処理の効率化をもたらします。さらには取引先としての信頼感が増すとともに、今後の受注にもつながっていきます。
以上のことからも、ビジネス社会における契約書の重要性がお解りいただけたと思います。
最後に、最近のビジネス契約における留意すべき点を一つだけ述べておきます。
| 典型契約 | ・民放に規定されている13種類の契約 贈与契約、売買契約、交換契約、消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約、雇用契約、請負契約、委任契約、寄託契約、組合契約、終身定期金契約、和解契約 |
| 非典型契約 | ・典型契約以外の契約 ライセンス契約、フランチャイズ契約、出版契約、ソフトウェア使用許諾契約etc. |
| 混合契約 | ・2種類以上の典型契約の性質をもつ契約 ソフトウェア開発委託契約(請負契約+委任契約)etc. |
ビジネスの世界でなされる契約は上の表のとおり大きく3つに分類されます。しかし、そのほとんどが法律化された典型契約ではなく、非典型契約や混合契約です。つまり、最近のビジネスで取り交わされるライセンス契約などのものは、そのほとんどが複雑な利害関係の絡む契約です。
契約に関する法律は、その性格上整備されるまでに時間がかかるため、最近のビジネスモデルであればあるほど、契約上の法規制そのものが存在しないこともよくあります。
ですから、新しいビジネスモデルであればあるほど、その契約においてビジネスモデルが正確に反映された契約書の作成が重要になってきます。
↑トップへ戻る
3.契約書の基本構成とその作り方
契約書の構成は、法律で決められている訳ではありません。しかし、ビジネスを円滑にすすめるには契約内容がわかりやすくなければなりません。
そのため、契約書の構成はとても重要になってきます。
では契約書を作成するにあたって、どのような構成がわかりやすいのでしょうか?
契約書の作成にあたってポイントとなる、7つの項目を次にあげます。
| ①タイトル | 内容が反映されたタイトルにする |
| ②前文 | 契約に至った事情を記載 |
| ③総論 | 目的として契約の概要を記載し、解釈に違いが生じる可能性がある用語を定義づける |
| ④主要条項 | それぞれの契約の特色を表す条件を規定する 簡単に説明するとサービス内容 |
| ⑤一般条項 | 一般的なビジネス契約においてよくある典型的な条件を規定する主なものは、金銭の支払い、期間、契約の解除とその後の取扱について損害が発生した場合、相殺予約について、個人情報や秘密情報について、裁判所の管轄について、第三者への委託について、その他注意すべきこと |
| ⑥後文 | いつ契約を結んで何通作ったかを記載する |
| ⑦署名欄 | 記名または、署名したうえで押印する ちなみに、記名はパソコンで既に印字されたところに押印する方法で、署名は、直接、名前などを契約者が書いて押印する方法です。 ただし、署名の場合は、筆跡鑑定などで本人が特定できますが、記名押印の場合だと、その特定が難しくなります。例えば、印鑑が盗まれた場合、盗んだ印鑑を押印して偽造された契約書かの判断が難しくなります。 |
文字だけだと解りづらいので簡単に実際の契約書の構成例をあげてみましょう。
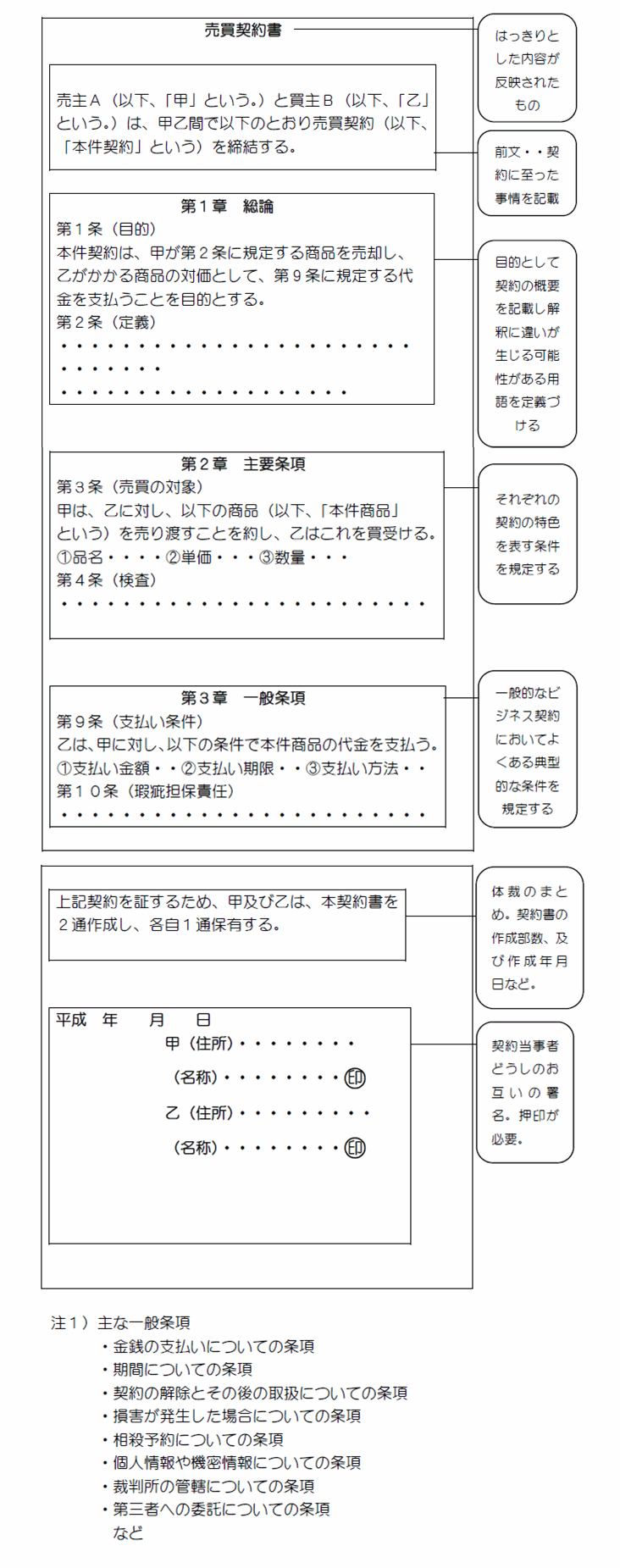
↑トップへ戻る
以上のような形が一般的な契約書の構成になります。
さて、最後にこの契約書を仕上げるにあたって、留意しておかなければならない点が3つあります。
最初の2つは押印と収入印紙についてです。
まずは押印から。
契約書に印鑑を押す場合は5つありそれは以下のとおりです。
| 契印 | 契約書が2枚以上にわたる場合、書類をとじた部分に押す |
| 割印 | 2通以上契約書を作った時に、2通にまたがって押す |
| 消印 | 印紙にまたがって押す |
| 捨印 | 訂正を簡単にするため、余白に押す |
| 訂正印 | 契約書の訂正の際に修正した文字ごとに押す |
次は収入印紙です。
契約書の作成は全て最後の署名押印で完結するものではなく、契約内容の性質上、財務省の規定に従って収入印紙を貼らなければならないものがあります。
収入印紙を貼らなくてはいけない契約書の例
①不動産売買契約書 ②土地賃貸借契約書 ③金銭消費貸借契約書
④著作権譲渡契約書 ⑤特許権譲渡契約書
上記のような収入印紙が必要な契約書の場合、契約書のわかりやすい箇所(一般的には、1ページめの右上)に貼り、台紙と印紙にまたがるように消印をおします。
収入印紙は、財務省が、租税、手数料その他の収納金の徴収のために発行する証票です。
契約書に関しても、印紙税法に定める課税標準と税率をもとに印紙税を納付します。
印紙税額の一覧に関しては、以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/
なお、収入印紙が貼られていなくても契約書自体は有効です。違反しているのは契約の内容ではなく収入印紙を貼らなかったという行為に過ぎません。
つまり、契約書に収入印紙が貼られているか否かという問題は、契約内容の問題ではなく課税文書であるにもかかわらず必要な税金を納めていないという納税の問題となります。
ただその場合、過怠税が発生してしまいます。収入印紙が貼ってあっても消印のない場合も同様なので、くれぐれも注意してください。
そして、最後の一つは契約書の修正方法です。
↑トップへ戻る
契約書を修正する3つの方法
①契約書を作り直す
契約は、日付が新しいものが有効になるので、大きな修正が出てしまった場合には、新しく作り直してしまいましょう。
②訂正印を押す
わずかな修正のときの一般的な方法です。1箇所や2箇所の場合は、新しく作るよりも訂正印で修正してしまうのが便利です。
③捨印を押す
契約者全員が契約書の余白に捨印を押すことで、契約書の内容を修正できるようになります。一度押せば何度でも訂正が出来るので、使い方によっては非常に便利です。ただし、捨印が押してあることで契約者の一方が契約書を自分に有利な内容に書き換えてしまうおそれがありますので、なるべく①と②の方法が良いでしょう。
以上契約書についての基本的なことをここまで説明してきました。
しかし、ビジネスのパターンが様々あるように、そこそこで交わされる契約書にもさまざまなパターンがあります。
そこで、以下、代表的ともいえるようなビジネスパターンの中からいくつかの契約書例を取り上げてより具体的に、契約書のあり方を見ていきたいと思います。
なお、その前に契約書で使われるいくつかの用語を説明しておきます。
| 用語 | 意味 |
| 契約上の地位の譲渡 | 契約当事者の地位を移転すること |
| 契約締結費用の負担 | 契約締結費用をいずれの当事者が負担するかについて定めた条項 |
| 身元保証 | 雇主と第三者との間で、従業員の行為によって雇主が損害を受けた場合に第三者が賠償することを約束する法律関係 |
| 著作者人格権 | 著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称 |
| 保証金 | 契約を守ることを担保するために支払う金額 |
| 法廷記載事項 | 法律により記載することが定められている事項 |
| 解除事項 | 一定の事実が発生した時に、債権者が何らかの催告をすることなく、ただちに契約を解除することができることを定めた条項 |
| 瑕疵担保責任事項 | 売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合に、売主が飼い主に対して負う責任について定めた条項 |
| 期限の利益喪失条項 | 債務者がその信用を損なうような一定の事実が生じた場合に、債務者がただちに金額を弁済しなくてはならなくなる特約を定めた条項 |
| 協議条項 | 契約者双方の信頼関係に基づき、契約書に定めのない問題等が発生した場合には、当事者間の協議でその解決を図ることを定めた条項 |
| 原状回復条項 | 賃借人に対して、建物明け渡し時に原状に復旧させる義務を負わせるなどを定めた条項 |
| 公租公課条項 | 国または地方公共団体によって公の目的のために賦課される金銭を、いずれの当事者が負担するかについて定めた条項 |
| 合意管轄条項 | その契約について裁判を起こす場合に、実際に裁判を行う裁判所の管轄を決めておく条項 |
| 遅延損害金条項 | 支払い期限に遅延した場合に、法律上、損害賠償として当然に支払うべき金利について定めた条項 |
| 任意処分条項 | 買主が商品を引き取らない場合の処理について定めた条項 |
| 秘密保持条項 | 契約当事者間で高度な秘密情報のやり取りが行われる際に、情報の漏えいを禁止することを定めた条項 |
| 品質保証期間条項 | 取引対象となる目的物において、発注者が要求する品質水準を維持することを受注者に保証させることを定めた条項 |
↑トップへ戻る
契約書の文例
実際に文例をあげて説明に入る前に、まず最初に、大まかな契約の種類と契約の条件に関しての用語を表にまとめておいたので見てください。| 用語 | 意味 |
| 委任契約 | 法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力が発生する契約 |
| 請負契約 | ある仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束することによって効力が発生する契約 |
| 寄託契約 | 相手方のために保管をすることを約束して、ある物を受け取ることによって効力が発生する契約 |
| 組合契約 | 各当事者が出資して共同の事業を営むことを約束することによって効力が発生する契約 |
| 雇用契約 | 当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約束し、相手方がその報酬を与えることを約束することによって効力が発生する契約 |
| 交換契約 | 当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約束することによって効力が発生する契約 |
| 使用貸借契約 | 無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約束して、相手方からある物を受け取ることによって効力が発生する契約 |
| 終身定期金契約 | 自己、相手方または第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方または第三者に給付することを約束することによって効力が発生する契約 |
| 出版契約 | 著作権者が出版者に著作物の出版を一任し、出版者がその出版の義務を負う契約 |
| 消費貸借契約 | 種類・品質・数量が同じものをもって返還をすることを約束して、相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力が発生する契約 |
| 贈与契約 | 自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力が発生する契約 |
| ソフトウェア使用許諾契約 | ソフトウェアなどの開発者やメーカーとユーザーとの間で取り交わされる契約 |
| 賃貸借契約 | ある物の使用および収益を相手方にさせることを約束して、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約束することによって効力が発生する契約 |
| 売買契約 | ある財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束することによって効力が発生する契約 |
| ライセンス契約 | 特許や実用新案をはじめとする知的財産権について、その権利者と第三者との間で結ばれる権利の実施許諾に関する契約 |
| 和解契約 | 当事者が互いに譲歩をして、当事者間にある争いをやめることを約束することによって効力が発生する契約 |
| 再実施権 | ライセンシー(免許を受けた人)が第三者にライセンスを許諾する権利 |
| 実施料 | 特許されている発明などを実施させてもらうための対価=ライセンス料 |
| フランチャイズ権 | フランチャイズ店を経営する権利 |
| ロイヤルティー | 特定の権利を利用する利用者が、権利を持つものに支払う対価(主に、特許権、商標権、著作権などの知的財産権の利用に対する対価) |
↑トップへ戻る
文例1.物の売買に関する契約
1)商品の購入、及び売却契約内容
売主A社が買主B社に部品(製品)を売却し、買主Bはその対価として、金銭を支払う。
契約の決定事項
①売買の対象(品名、単価、数量)の決定
②支払条件(支払金額、支払期限、支払方法)の決定
③所有権移転と危険負担の決定
④引渡しの条件(検査、引渡期日、引渡場所)の決定
その他契約書に盛り込むべき事項
瑕疵担保責任・期限の利益喪失・任意処分・遅延損害金・解除・合意管轄・協議
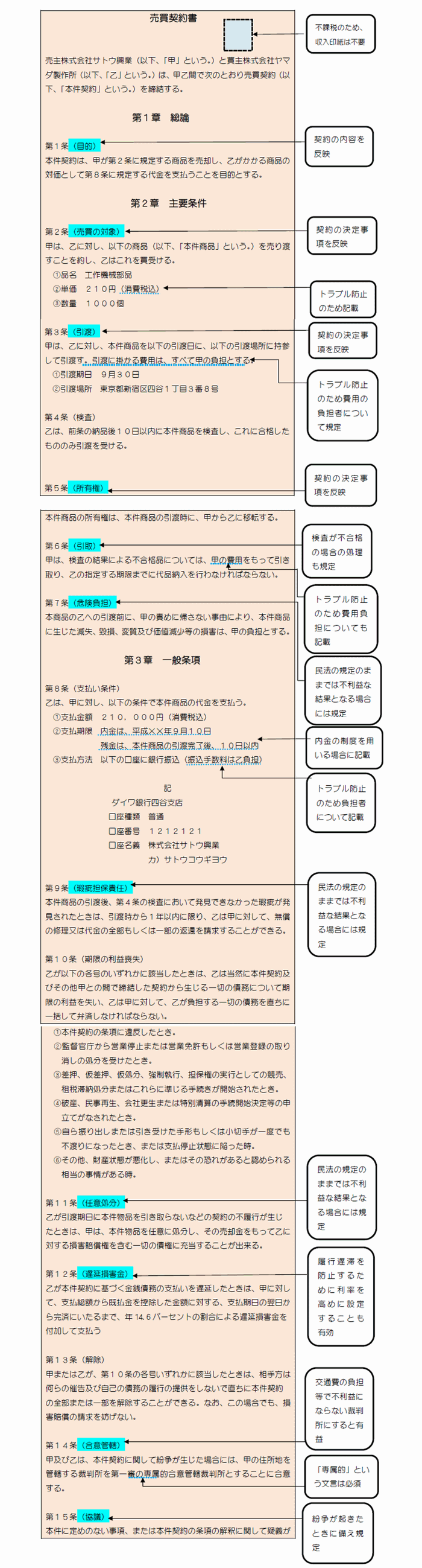
↑トップへ戻る
2)不動産を購入、売却
契約内容
土地(不動産)の持主A社が買主B社に土地を売却し、その対価として金銭を受け取る。
契約の決定事項
①売買の対象となる不動産の特定
②不動産の面積の特定
③所有権移転(登記)の決定
④引渡の条件(検査、引渡期日、引渡場所)の決定
⑤残置物の所有権放棄の決定
⑥担保権等の抹消の決定
⑦危険負担の決定
その他契約書に盛り込むべき事項
支払条件・公租公課の分担・無条件解除・不履行による解除・契約締結費用の負担・合意管轄・協議
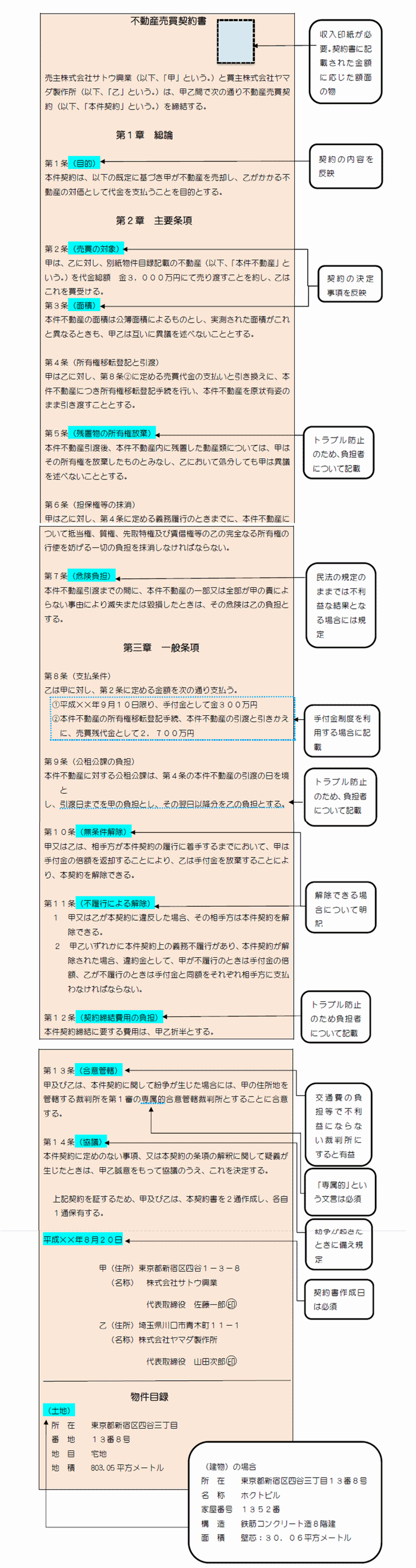
↑トップへ戻る
文例2. 不動産の貸借に関する契約
1)事務所の貸借契約内容
賃貸人A社が、賃借人B社に不動産を賃貸する。その際CがB社の連帯保証人となる。
契約の決定事項
①賃貸借の対象となる不動産の特定
②賃貸借の条件(使用目的、契約期間、保証金、賃料、共益費)の決定
③保証金の決定
その他契約書に盛り込むべき事項
支払条件・解除・原状回復及び明渡・契約期間・連帯保証人・合意管轄・協議
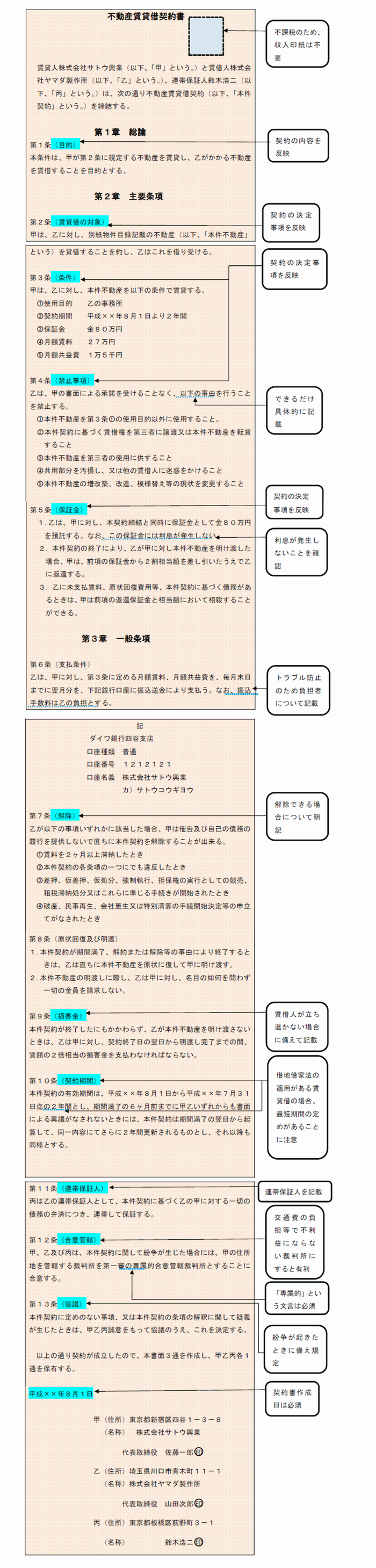
↑トップへ戻る
2)土地の貸借
契約内容
賃貸人A社が、CがB社の連帯保証人となって賃借人B社に土地を賃貸する。
本件契約の決定事項
①賃貸借の対象となる不動産の特定
②賃貸借の条件(使用目的、契約期間、保証金、賃料、共益費)の決定
③保証金の決定
④禁止事項の決定
⑤契約期間の決定(30年以上か確認)
その他契約書に盛り込むべき事項
支払条件・解除・原状回復及び明渡・契約期間・連帯保証人・合意管轄・協議
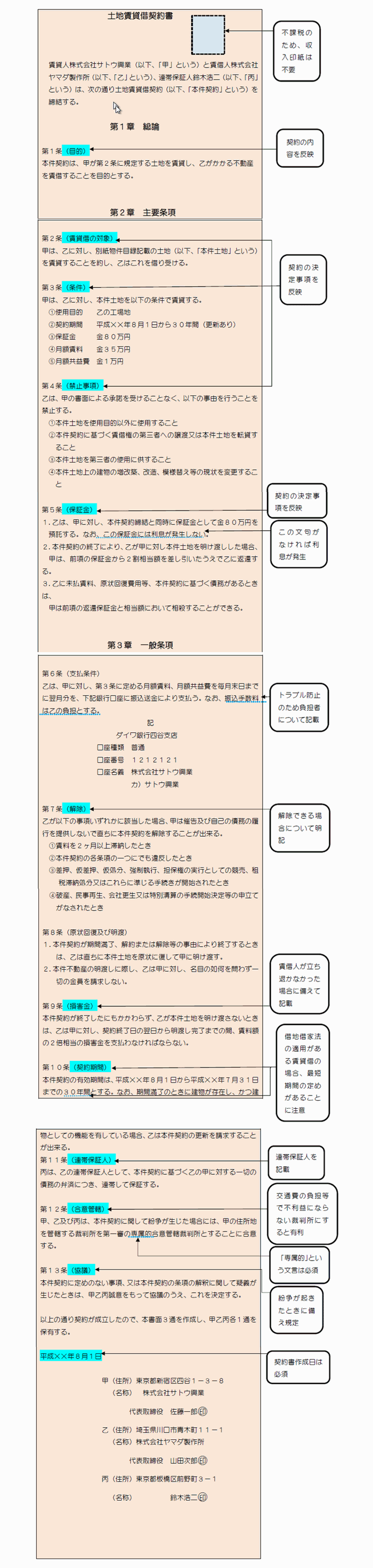
↑トップへ戻る
文例3.金銭の貸し借りに関する契約
契約内容A社とB社との間で金銭を貸借する。
本件契約の決定事項
①貸付金額の特定
②利息(支払い金額、支払期限、支払方法)
③弁済条件の決定
その他契約書に盛り込むべき事項
弁済方法・期限の利益喪失・遅延損害金・届出義務・合意管轄・協議
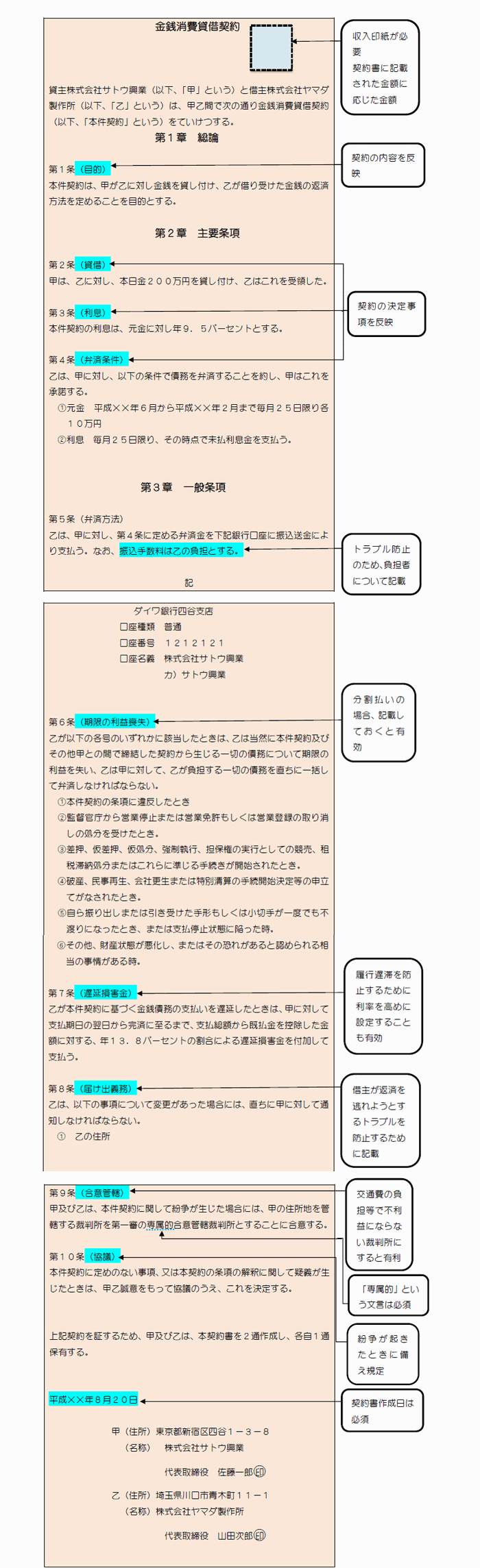
↑トップへ戻る
文例4.企業や個人に対する特定業務の依頼
1)フランチャイズの契約契約内容
A社はB社に対し、フランチャイズ権を付与して経営指導を行い、B社はA社に対し、ロイヤルティーを支払う。
本件契約の決定事項
①フランチャイザーの義務の決定
②フランチャイジーの義務の決定
③加盟金の決定
④保証金の決定
⑤ロイヤルティーの決定
その他契約書に盛り込むべき時期
解除・期限の利益喪失・契約終了後の処理・権利譲渡の禁止・更新条項・合意管轄・協議
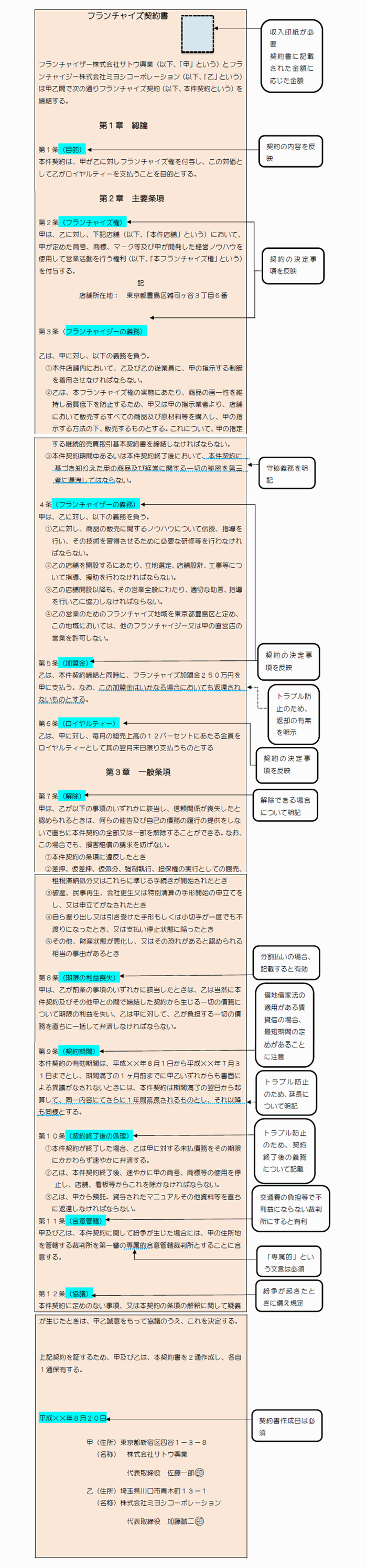
↑トップへ戻る
2)代理店契約
契約内容
A社はB社に対し、商品販売の代理権を付与し、B社は、その商品販売の対価として、A社から手数料を受け取る。
本件契約の決定事項
①商品の代理権の付与
②商品の販売方法の決定
③手数料(金額、算定方法、支払方法)の決定
その他契約書に盛り込むべき事項
販売代金の送金・保証金・期限の利益喪失・解除・遅延損害金・契約期間・契約終了後の処理・合意管轄・協議
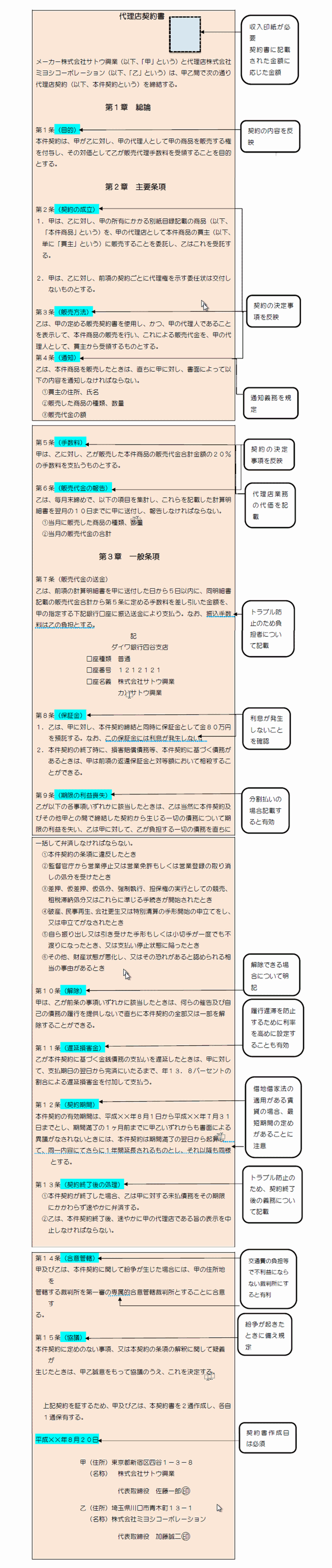
↑トップへ戻る
3)業務の委託、受託に関する契約
契約内容
A社はB社に対し、給与計算に関する業務を委託し、B社はその業務の結果を提供する。
本件契約の決定事項
①委託する業務内容の特定
②委託料の決定
③報告義務の決定
④再委託の禁止を定める場合の内容の特定
その他契約書に盛り込むべき事項
委託料の支払方法・期限の利益喪失・解除・契約期間・契約終了後の処理・合意管轄・協議
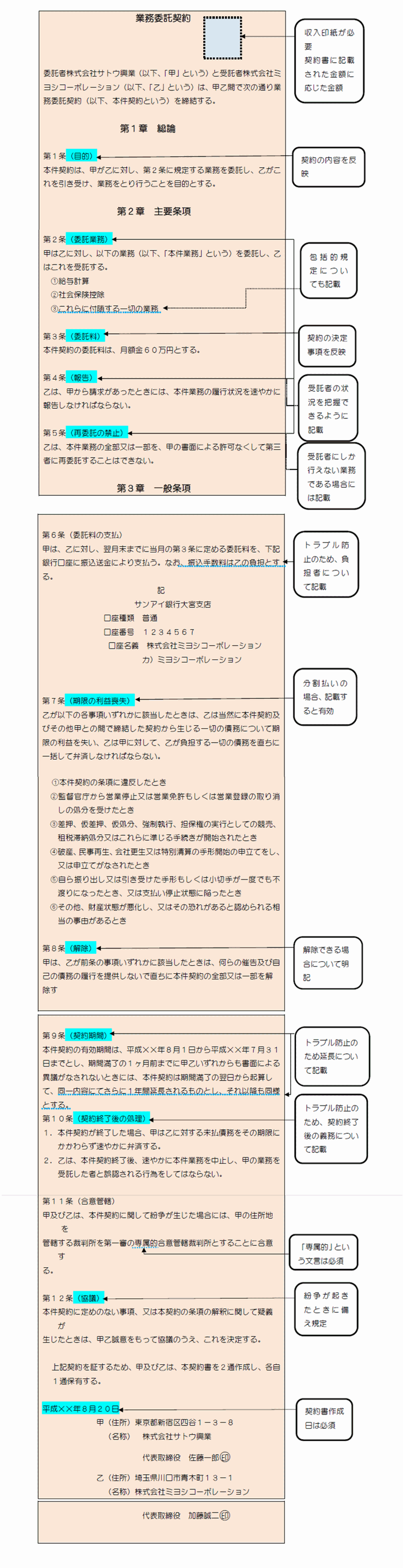
↑トップへ戻る
4)設備、機器等のリース契約
契約内容
A社はB社に対し、CがB社の連帯保証人となって設備、機器を賃貸し、B社は賃料を支払いその設備、機器を借り受ける。
本件契約の決定事項
①リースの条件(対象物件、契約期間、保管場所、リース料等)
②禁止事項の決定
③保守管理の決定
④保証金の決定
その他契約書に盛り込むべき事項
支払方法・契約終了・連帯保証人・契約期間・合意管理・解除・協議
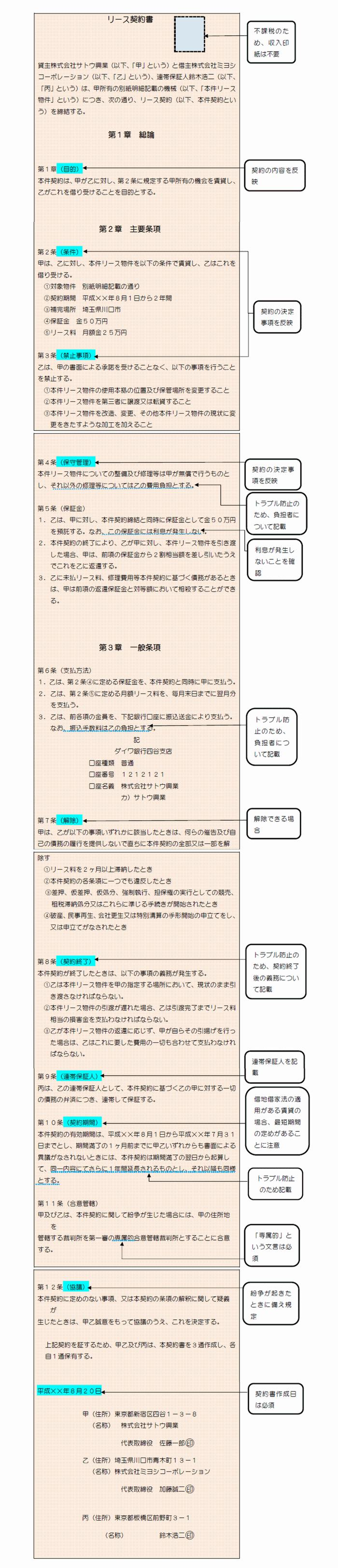
↑トップへ戻る
文例5.インターネット関係の取引
1)自社サイトの広告主探し契約内容
A社がB社に対して、B社のビジネスに適合した広告主を発見、紹介する。
本件契約の決定事項
①主要義務の決定
②本サービスの代理店手数料の決定
③営業活動の範囲の決定
④申込方法の決定
⑤支払期日及び支払方法の決定
⑥請求業務の確認
⑦運営体制の確認
その他、契約書に盛り込むべき事項
解除・合意管轄・協議
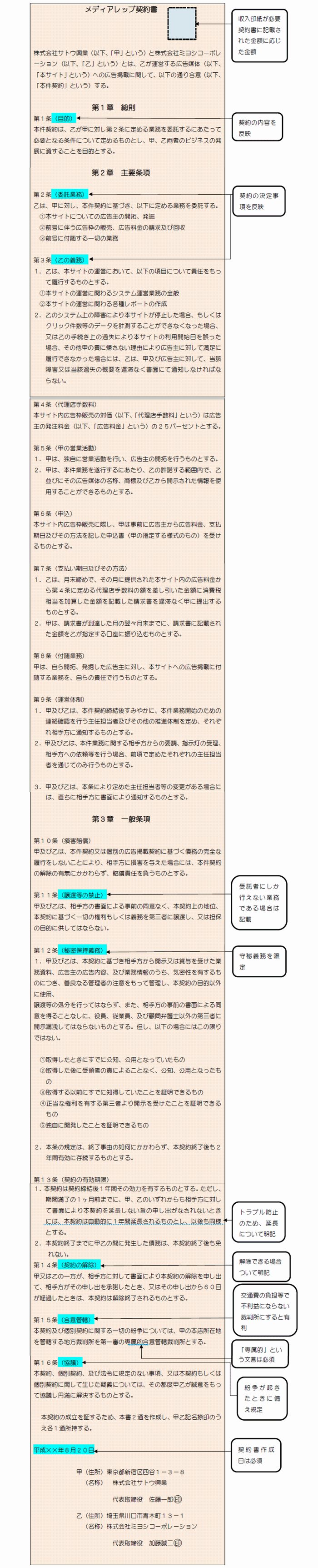
↑トップへ戻る
文例6 人事労務関係の契約
1)従業員の雇用契約内容
A社がBを従業員として雇い入れ、BはA社に労務を提供する。
本件契約の決定事項
①労働条件通知書による労働条件の決定
②誓約事項の確認
③懲戒、退職、解雇事由の確認
その他、契約書に盛り込むべき事項
合意管轄・協議
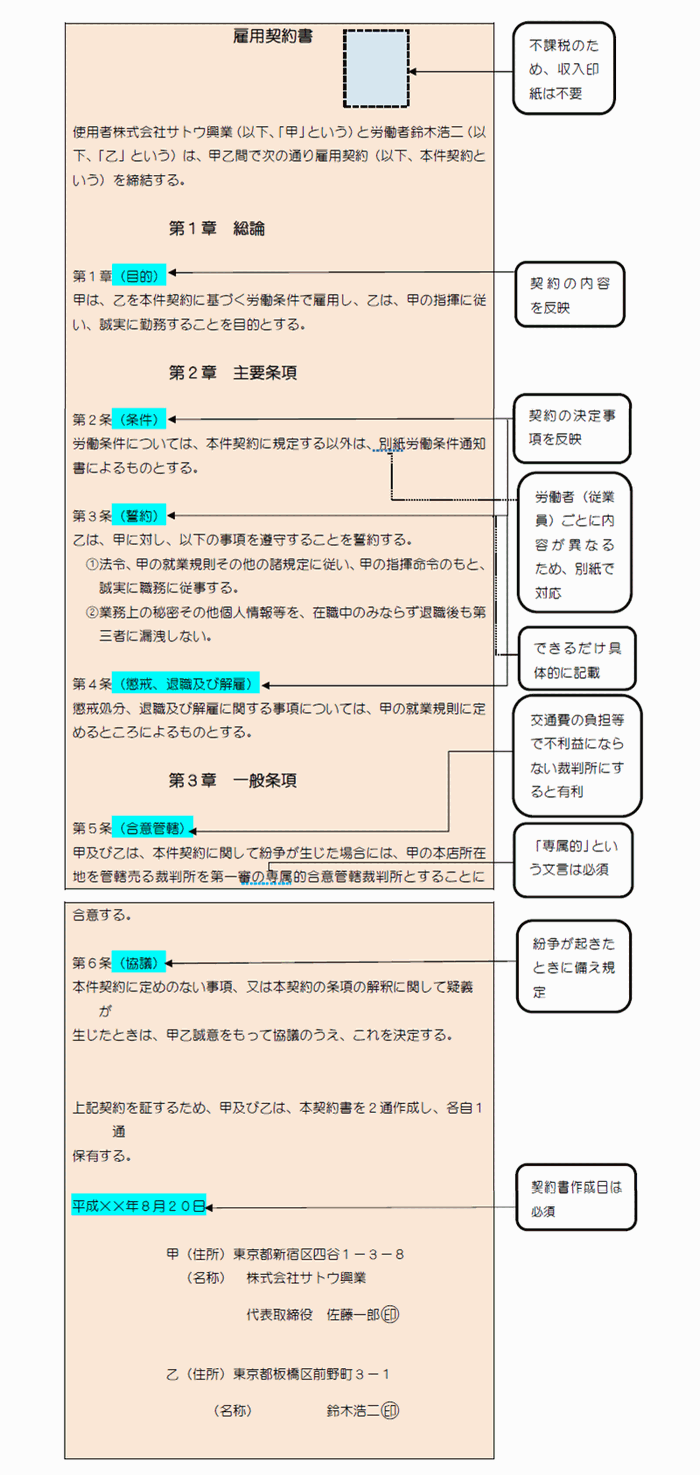
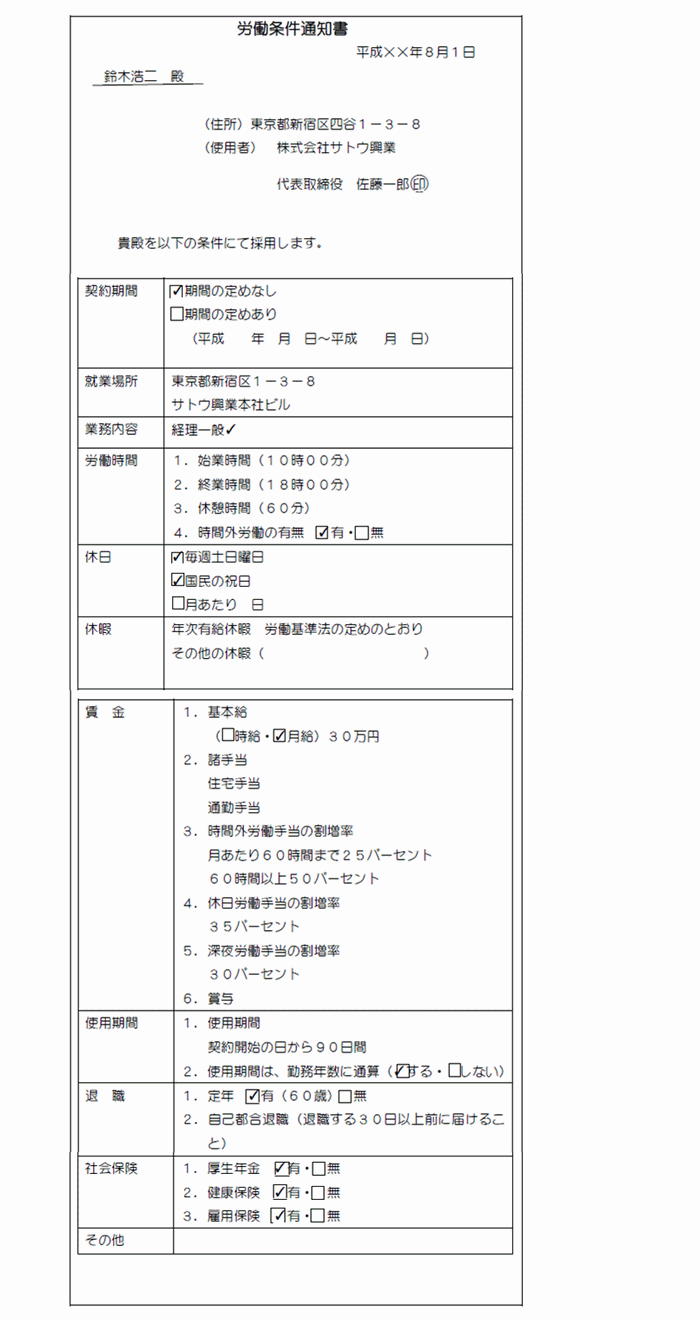
↑トップへ戻る
2)従業員の出向
契約内容
A社はB社に対し、A社の従業員Sを出向させ、B社はSとの間で新たに労働契約を締結し、Sから労務の提供を受ける。
本件契約の決定事項
①出向の条件(就業場所、出向期間、業務内容)
②賃金等の負担の決定
③社会保険等の負担の決定
④復職に関する決定
その他、契約書に盛り込むべき事項
合意管轄・協議
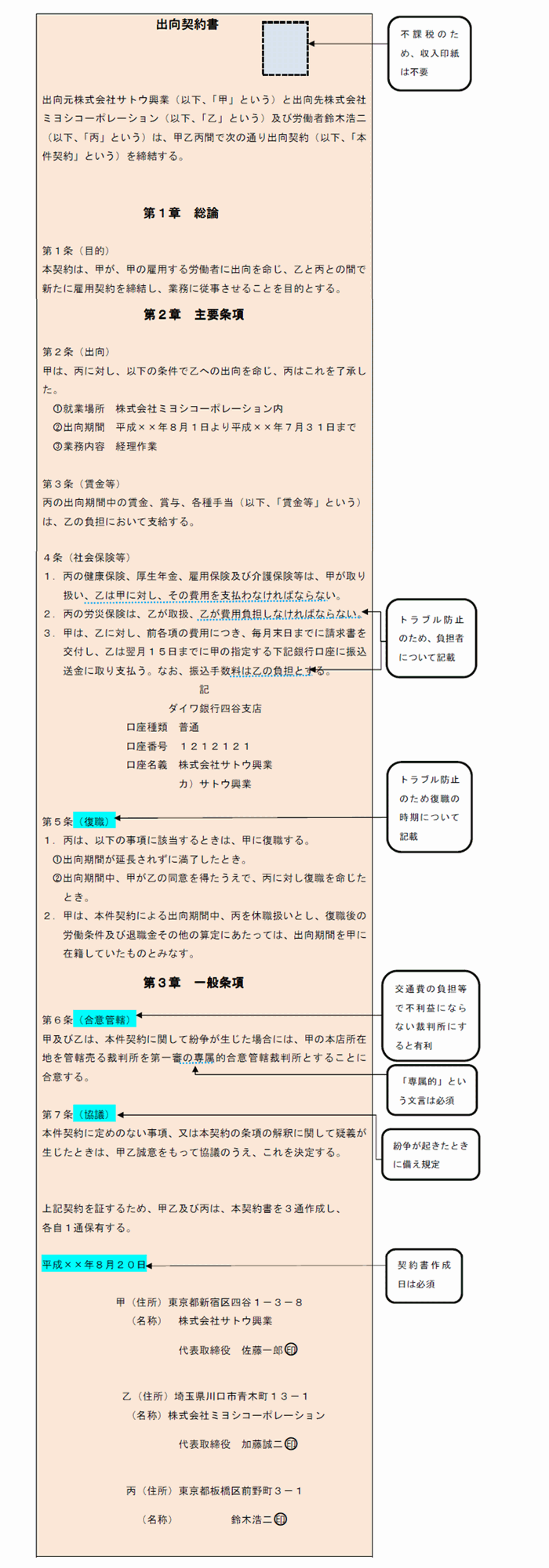
↑トップへ戻る
文例7 知的財産に関する契約
知的財産とは、知的な活動から生み出された財産権のことをいいます。具体的には、作家・音楽家などの芸術家が生み出した作品、個人や会社などが研究開発により生み出した商品、サービス・ブランドや経営営業上のノウハウなどです。
これらの知的財産は当然その利用によって利益を発生します。そこで、それらを生み出した者を保護しその利益を確保するための権利として、知的財産権が認められています。
ここでは、その知的財産にかんするいくつかの契約書の例を挙げていきますが、主な知的財産権には以下の5つのものがあります。
| 名称 | 権利の内容 | 権利行使の効果 | 権利化 | 期間 |
| 実用新案権 | ある機能、性能を実現するために考案した構造、形状を登録し、独占使用できる。 | 手続きが必要 | 出願から10年 | |
| 特許権 | 発明品を登録し、独占利用できる。 | 独占的に技術を利用して、商品等の差別化を図ることができる。 |
手続きが必要 | 原則、出願から20年 |
| 意匠権 | 考案した意匠(デザイン)を登録し、独占使用できる。 | 似たデザインを作った者に対して、使用の差し止めや損害賠償を求めることができる。 |
手続きが必要 | 登録から20年 |
| 商標権 | 会社のブランド・ロゴマークなど独占使用できる。 | 似たブランドマークを使用した者に対して、使用の差し止めや損害賠償を求めることができる。 |
手続きが必要 | 登録から10年 |
| 著作権 | 文芸、学術、美術、音楽など創作物の作者の権利で、複製権、譲渡権などがある。 | 他者は、著作者の許諾を得なければ著作物を使用することができない。 |
手続きは不要 | 原則、著作者の死後50年 |
1)原稿執筆の依頼
契約内容
ルポライターAは、旅行記の原稿を執筆し、B社がそれを出版する。
本件契約の決定事項
①作品の納入の方法の決定
②作品の著作権(誰に帰属するか)の決定
③所有権移転と危険負担の決定
④出版社の利用方法の特定
⑤著作人格権の特定
⑥著者が第三者から損害賠償請求を受けた場合の保証の決定
その他、契約書に盛り込むべき事項
報酬・契約終了後の処置・秘密保持・権利義務の譲渡禁止・合意管轄・解除・協議
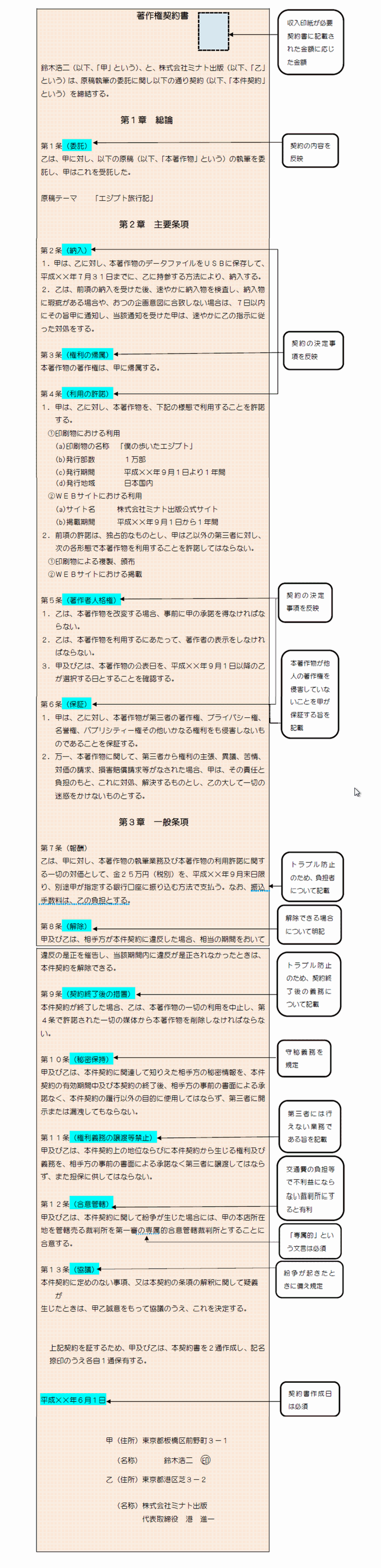
↑トップへ戻る
2)特許権の使用の許諾
契約内容
ソフトウェアに関連した特許権を持っているA社(ライセンサー)は、B社にその特許権を独占的に使用させ、実施料を受領する。
本件契約の決定事項
①実施権設定登録方法の決定
②実施権の範囲の決定
③実施料(金額、支払方法)の決定
④実施報告の頻度の決定
⑤再実施の可否の決定
⑥改良発明を加えたときの対応の決定
⑦ライセンサーからライセンシーへの技術援助の決定
⑧侵害行為があった場合の対応の決定
⑨特許番号の表示の決定
その他、契約書に盛り込むべき事項
秘密保持・解除・実施料の不返還・合意管轄・協議
3)意匠権の譲渡
契約内容
アパレル事業から撤退することとなったA社は、不要となったアパレルに関する意匠権をB社に譲渡することにした。
本件契約の決定事項
①登録手続の方法の決定
②登録料の負担の決定
その他、契約書に盛り込むべき事項
秘密保持・解除・合意管轄・協議
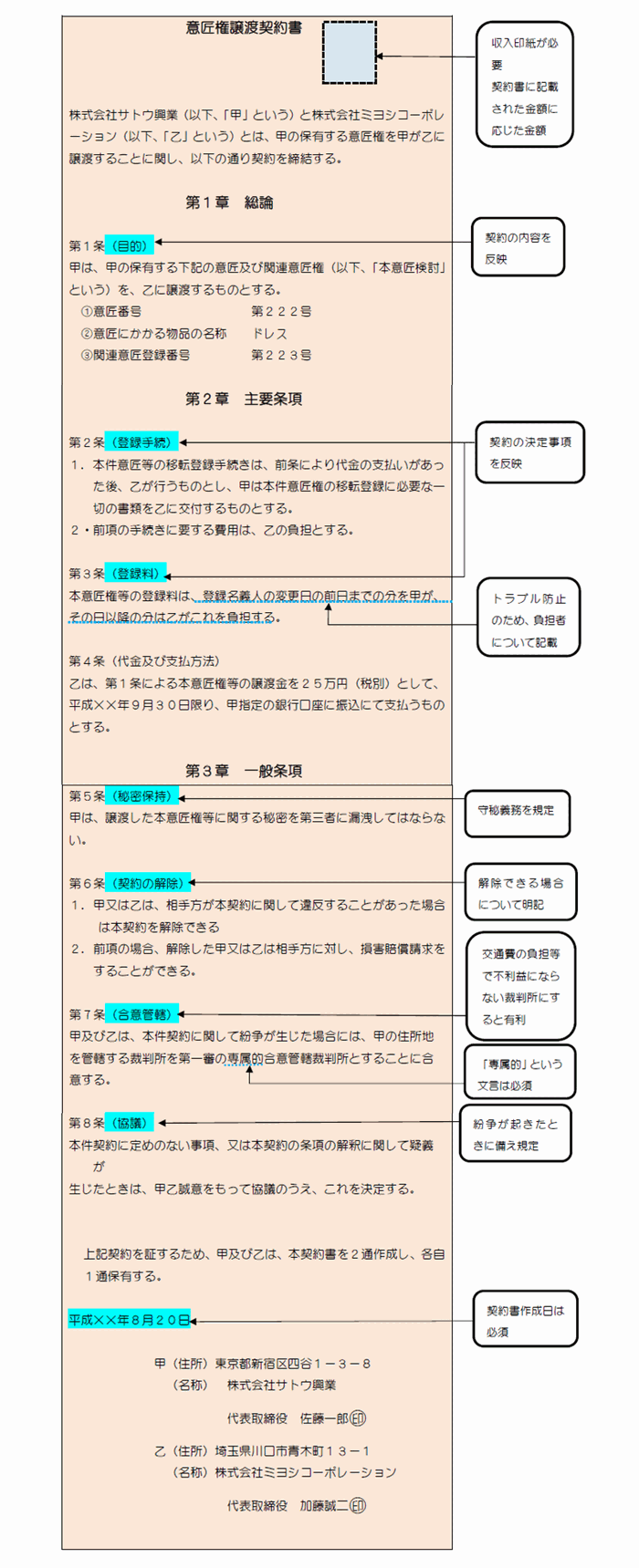
↑トップへ戻る
文例8 会社間の取引に関する契約
1)他社への事業の譲渡契約内容
A社はB社に対して、長年営んできたレストラン事業を譲渡する。
契約の決定事項
①譲渡する財産の特定
②譲渡の日付の決定
③譲渡の対価(金額、支払方法)の決定
④引き渡し時期の決定
⑤譲渡手続きの決定
⑥善管注意義務の確認
⑦従業員の取扱の決定
⑧租税公課の取扱の決定
⑨株主総会の承認事項の確認
⑩事業が変更した場合の解除の決定
その他、契約書に盛り込むべき事項
秘密保持・合意管轄・協議
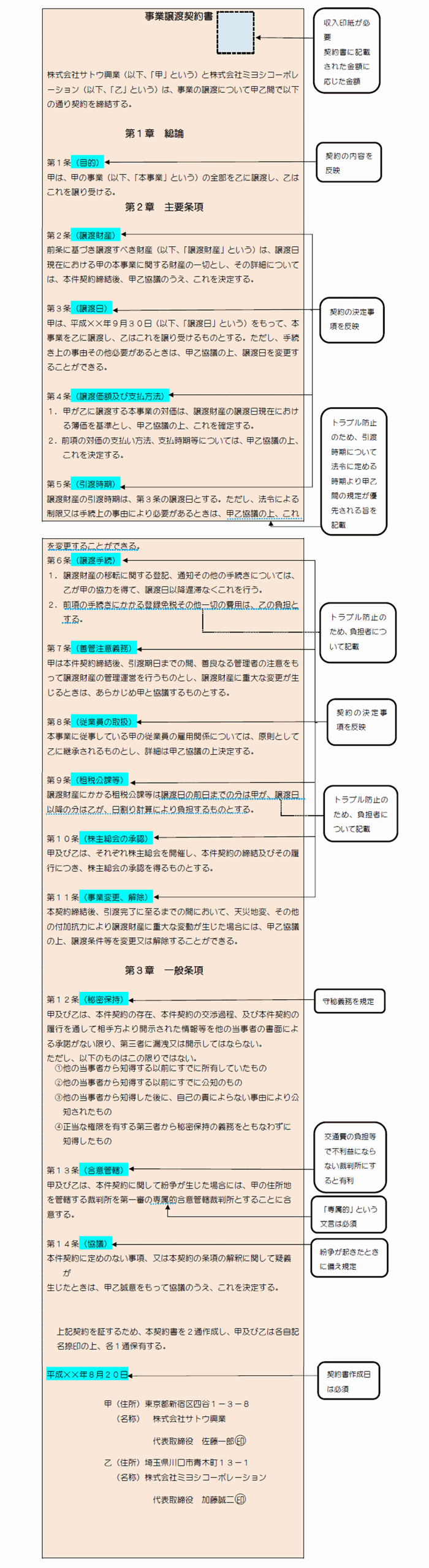
↑トップへ戻る
2)会社の合併・吸収
契約内容
A社は、B社を吸収合併する。
本件契約の決定事項
①合併に際して発行する株式(数、額)の決定
②合併後の資本金の決定
③合併承認総会の決定
④合併期日の決定
⑤合併による財産の引継ぎの決定
⑥善管注意義務の確認
⑦合併交付金の支払い
⑧2社の株主への利益配当の金額の決定
⑨従業員の処遇の決定
⑩合併後の役員の決定
⑪役員の退職慰労金の決定
その他、契約書に盛り込むべき事項
契約の変更、解除・契約の効力・合意管轄・協議
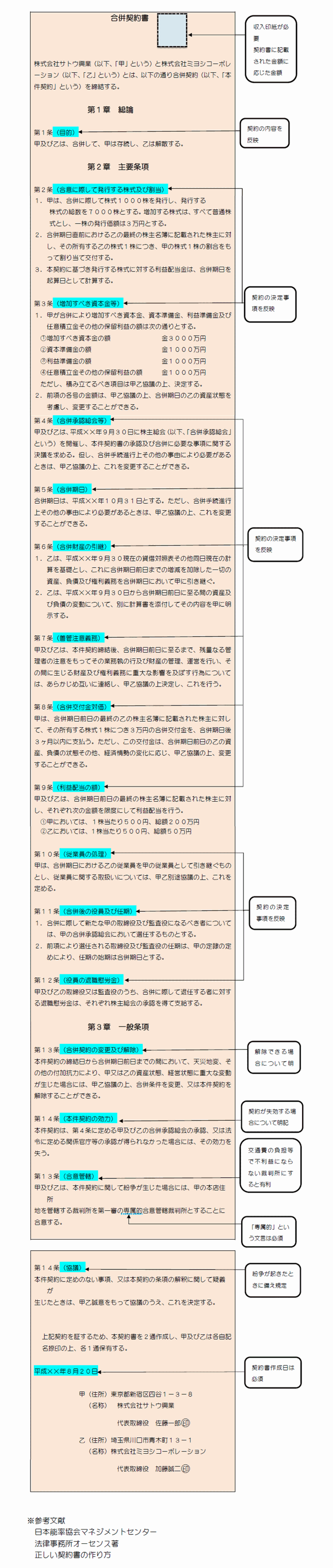
↑トップへ戻る